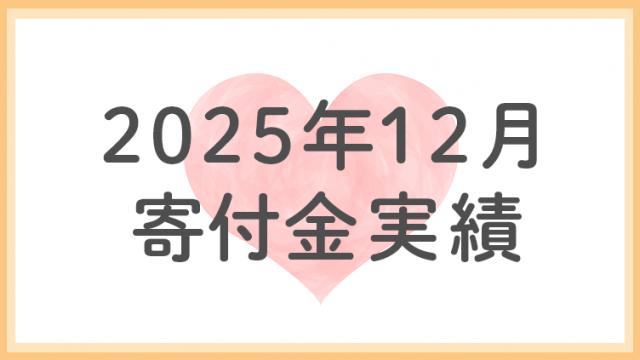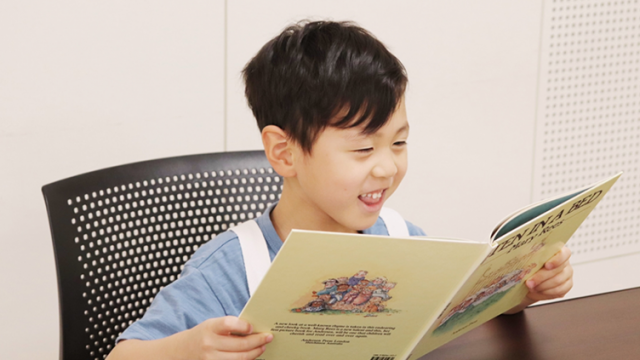寄付金控除のやり方を初心者向けに解説!確定申告の手順や必要書類も詳しく紹介

寄付金控除は、寄付したお金が一定額控除される制度です。
初めての人にとっては難しそうに感じるかもしれませんが、手順を知れば誰でも簡単に申請できます。
本記事では、寄付金控除の基本から確定申告のやり方まで丁寧に解説します。
寄付金控除とは?初心者でもわかる基礎知識
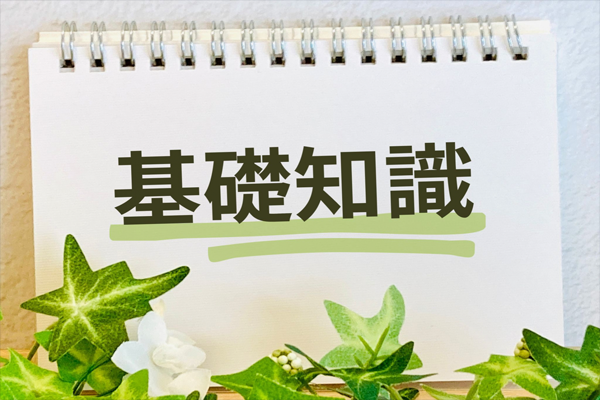
寄付金控除とは何か、どのような仕組みで控除されるのかを初心者にも分かりやすく解説します。
まずは制度の概要や種類から理解しましょう。
寄付金控除の制度の意味と仕組み
寄付金控除とは、個人が特定の団体に寄付をした場合に、一定金額を所得や税額から差し引いて税負担を軽くする制度です。
この制度を利用すると、寄付した分が一部税金から軽減されるため、社会貢献をしながら節税効果も得られます。
寄付金控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類があり、それぞれ控除額の計算方法や対象となる寄付が異なります。
まずはこの仕組みをしっかり押さえましょう。
寄付金控除の対象となる具体的な団体の種類
寄付金控除が認められる対象団体には、国や地方公共団体、公益社団法人や公益財団法人、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)などがあります。
また、ふるさと納税を含め、災害義援金や特定の社会福祉法人、教育機関や研究機関への寄付も控除の対象です。ただし、すべての団体が対象になるわけではありません。
控除の対象になるかどうかは国税庁や各団体の公式サイトで確認することが必要です。
所得控除と税額控除の違いと控除額の計算方法
寄付金控除には「所得控除」と「税額控除」があり、それぞれ控除の仕組みが異なります。
「所得控除」は寄付金額から2,000円を引いた金額を所得から差し引くもので、所得税率に応じて控除額が決まります。
一方、「税額控除」は(寄付金額-2,000円)×40%を税額から直接差し引けるため、所得税率に関係なく控除効果が明確です。
多くのケースで税額控除の方が有利になるため、選択する際は計算して判断しましょう。
寄付金控除を受けるための基本条件をチェック

寄付金控除を受けるためには、いくつかの基本条件を満たす必要があります。
制度を利用する前に、条件や対象範囲をしっかり確認しましょう。
寄付金控除の対象になる団体の調べ方と基準
寄付金控除の対象となる団体は国税庁や地方自治体の公式サイトで調べられます。
(国税庁寄附金控除)
主な対象団体は、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益財団法人・公益社団法人など、公益性が認められた団体です。
公益性のある活動をしていても、認定や承認受けていない団体は寄付金控除対象外の場合があります。
事前に公式サイトや団体に直接確認し、控除対象であるかどうかを確実に把握しておくことが重要です。
控除が認められる寄付金額の下限と上限額
寄付金控除を受けるためには、寄付した金額が年間で2,000円を超えている必要があります。
2,000円が自己負担分として設定され、それを超えた分が控除対象です。
控除額には所得金額の40%という上限が設定されています。
この上限を超える寄付をしても、超えた分は控除の対象にはなりません。
自分の所得金額を考慮しながら、適切な寄付額を設定し、効果的に控除を活用することが大切でしょう。
ふるさと納税以外で控除が受けられる寄付の種類
ふるさと納税以外でも、多様な寄付で控除を受けることが可能です。
たとえば、認定NPO法人や公益法人、災害支援の義援金などへの寄付も控除対象となります。
特定の教育機関や研究機関、社会福祉法人への寄付も控除を受けられます。
ただし、すべての団体が控除対象とは限らないため、事前に対象となるか公式サイトや団体に確認しましょう。
多様な寄付の方法を知り、効果的に控除を活用してください。
寄付金控除を受ける手続きと必要書類
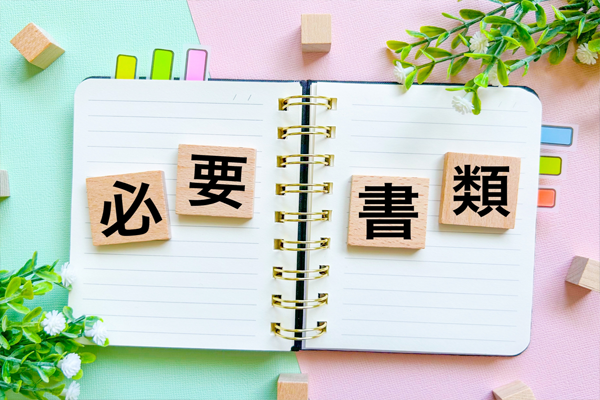
寄付金控除を実際に受けるためには、手続きや必要書類を理解して準備する必要があります。
初心者でも迷わずに申請できるように、丁寧に解説します。
寄付金控除の申請に必要な書類と入手方法
寄付金控除を受けるためには、寄付した団体から発行される「寄付金受領証」が必須です。
受領証には寄付金額、寄付の日付、寄付先団体の名称が明記されています。
寄付をした際に団体から自動的に送付される場合が多いですが、届かない場合や紛失した場合は団体に再発行を依頼しましょう。
また、確定申告を行う際は、この寄付金受領証を添付する必要がありますので、必ず大切に保管しておきましょう。
確定申告書の書き方と提出方法
寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告書には所得控除の場合は「寄付金控除」欄、税額控除の場合は「寄付金特別控除」欄にそれぞれ寄付した金額を記入します。
提出方法は、税務署に直接提出するほか、郵送やオンライン(e-Tax)でも可能です。e-Taxは自宅で簡単に申告が完了するため初心者にも便利でしょう。
提出期限は翌年の3月15日までなので、余裕をもって準備を進めることが大切です。
年末調整で寄付金控除が適用されない理由
年末調整では、通常、寄付金控除が適用されません。
年末調整は給与所得者が受けるものであり、医療費控除や寄付金控除など一部の控除は対象外だからです。
そのため、給与所得者でも寄付金控除を受けたい場合は、年末調整後に自分で確定申告をする必要があります。
寄付を行ったら忘れずに確定申告をして、控除を受けましょう。
確定申告をすることで、寄付金控除が適用され税金が還付されます。
寄付金控除を申請する際に間違いやすいポイント

寄付金控除を申請する際、初心者がよく間違えやすいポイントがあります。
スムーズな申告を行うため、申請時に注意すべきことをしっかりと理解しておきましょう。
控除対象となる寄付の期間と申告期限
控除対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの期間内に行った寄付のみです。
寄付の日付が翌年にずれ込んだ場合、その年の控除対象にはなりません。
申告期限は翌年の3月15日までですが、期限を過ぎると控除が認められない可能性もあります。
特に年末ぎりぎりの寄付は日付の管理に注意し、確定申告の準備も早めに行っておくことで、控除を確実に受けられるでしょう。
寄付金受領証の紛失や不備
寄付金控除の申請で最も多いトラブルは、寄付金受領証の紛失や記載内容の不備です。
寄付金受領証は、寄付控除を受けるために必要不可欠な書類のため、紛失すると控除が受けられなくなる可能性があります。
また、記載内容に漏れや誤りがある場合も申告が認められないことがあります。
受領証を受け取ったら内容をすぐに確認し、紛失しないよう安全な場所に保管してください。
万が一紛失した場合は速やかに寄付先団体へ再発行を依頼してください。
オンライン申告時の入力ミスや記載漏れ
オンライン(e-Tax)での確定申告時に多いのが入力ミスや記載漏れです。
特に寄付金額の入力ミスや受領証の添付忘れは控除が認められない原因になります。
オンライン申告では画面上で確認を行いながら入力できますが、数字の桁や寄付日の日付入力を間違えるケースも多いため注意が必要です。
送信前には入力内容を再度確認し、受領証のスキャン画像なども漏れなく添付したか確認してから送信しましょう。
寄付金控除を受けられる寄付はモノドネが簡単!

寄付金控除を受ける寄付を考えるなら、モノドネを利用するのもおすすめです。
モノドネは、自宅で不要になった物を送るだけで、その査定額が直接寄付金として活用されるサービスです。
自分で金銭を用意する必要がなく、気軽に社会貢献ができます。さらに、モノドネでの寄付は認定NPO法人など控除対象となる団体へ行われるため、寄付金控除の適用も受けられます。
物の整理と社会貢献を同時に行い、税金の優遇措置も受けられるモノドネをぜひ活用してみましょう。
まとめ

寄付金控除は初心者でも簡単に利用できる制度です。
寄付の対象や手続き、必要書類などをきちんと確認すれば、誰でも無理なく申告できます。
モノドネのような便利なサービスも活用しながら、社会貢献と税制メリットを同時に実現しましょう。
ぜひ気軽に寄付を始めてみてください。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?